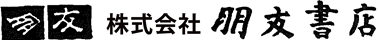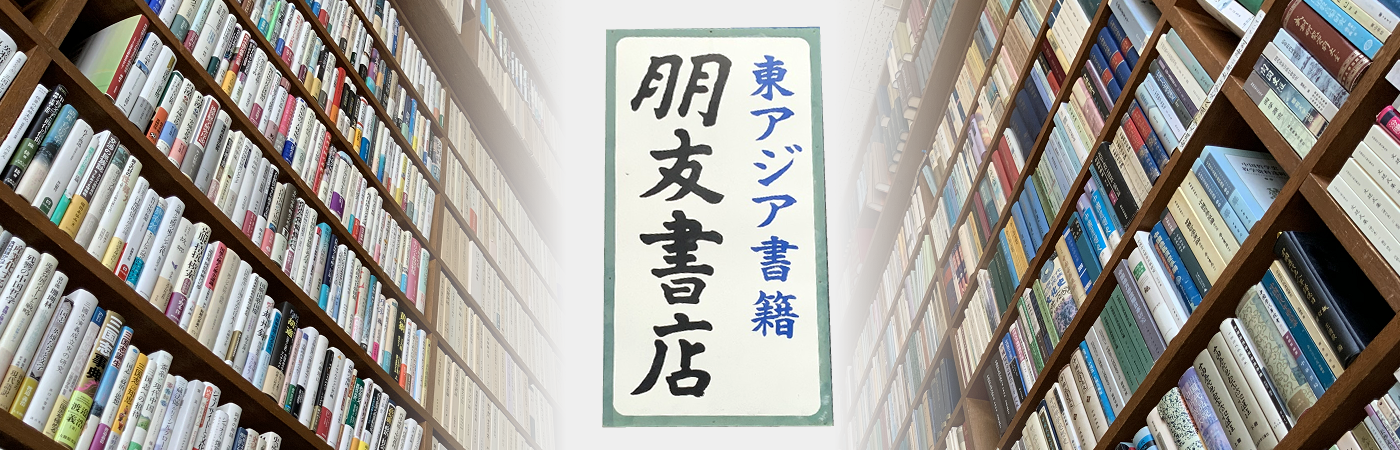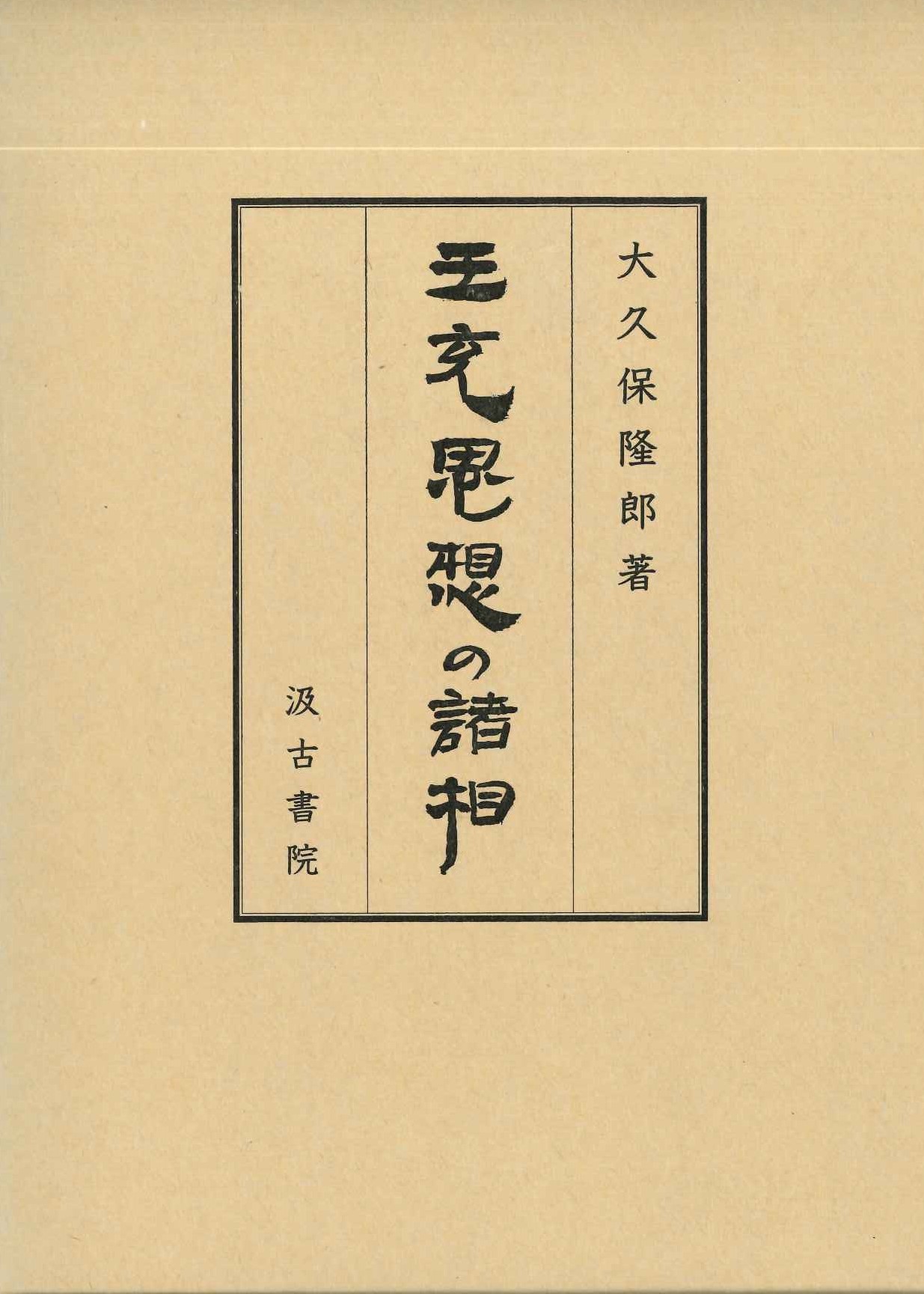日本
王充思想の諸相
日本
王充思想の諸相
- 出版社
- 汲古書院
- 出版年月日
- 2010.01
- 価格
- ¥13,200
- ページ数
- 779
- ISBN番号
- 9784762928734
- 説明
- ※出版年が古いので新本ですがヤケ・シミ・痛みがございます。
【はしがき】より
王充『論衡』研究の論文・著書はかなりの数がある。本書、文献目録はその一端である。わが国では佐藤匡玄著「『論衡』の研究」(創文社東洋学叢書、一九八一年)がある。後、三十年、漸くにして本書の上梓となった。旧稿の整理をしながら不備を補い、誤りを訂正するにかなりの時を必要とした。
本書の構成に欠くものは、一世紀に生きた王充の人となり、その生涯、周辺の人々やその時代についての記述、中国の研究所にいう「生平」である。私の王充研究は王充の思想研究と王充とその周辺の人々との絡み合い―評伝の試み―にあった。二部構成を企図したのである。両者は錯綜しあう事柄も多く、諸般の事情から思想の分野を「王充思想の諸相」として先に世に問うことにした。王充とその時代、評伝の試みは、後日に期することとした。本書は主として『論衡』本文の精査、解読を旨としている。解読考察の限界もあり、ただ紙面を費やした憾み、なきにしもあらずである。王充論衡には残された問題も多い。後の君子がこれを解き明かしてくれることを期待したい。
都、洛陽を遠く離れた会稽、上虞の地で王充は百篇を越える文章を書き残した。このエネルギーは何だったのか。著作の一つである『論衡』三十巻八十五篇(内一欠)は冒頭から遇不遇、人との出会いと運命の問題が問われている。貴賤・強弱・寿夭等々は夫婦の氣合の際、已に決定されていると説き、能力や操行の善し悪しとは無関係に初稟にすでに決していると説く。この定命論は多面的に教線をはる。
王充を著述に突き動かしたもの、それを一言でいえば「危機意識」である。国家秩序の崩壊に繋がるものとしての意識である。華文放流する浮薄な時勢から民衆を匡済し、道義的実誠の社会に帰するを求めたのである。この危機意識の対極にあったものは、夷狄異文化の伝播にあった。異文化とは「浮屠」の教えである。此岸の世界を苦海とし彼岸に涅槃を求めるブッダの教えであった。この夷狄文化に対し、王充は人々に儒教的古典文化の真実を涵養し、生活の安寧を希求したのである。そこには当然、強烈な古典的知識人としての民族意識と西域異民族への蔑視。異端視がある。ここに王充思想を読み解く鍵がある。これが王充的思想解明の筆者の視点である。本書からその一端を読み取って頂きたい。仏教の東伝については後日を期することにする。